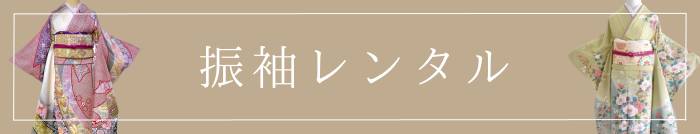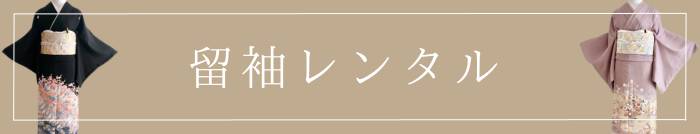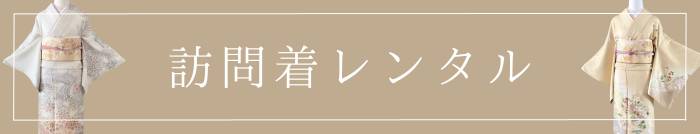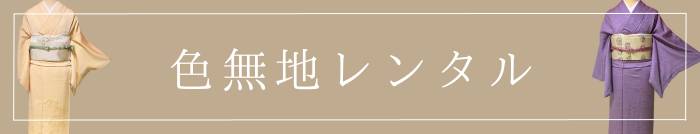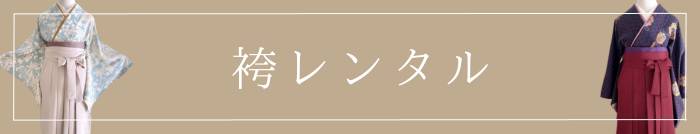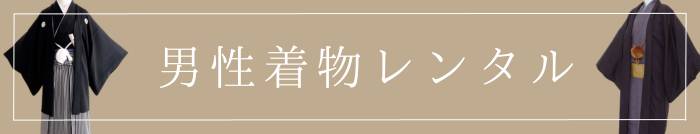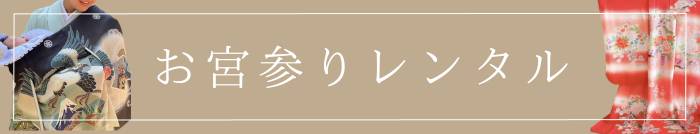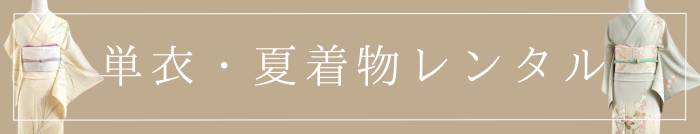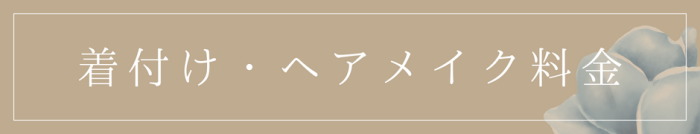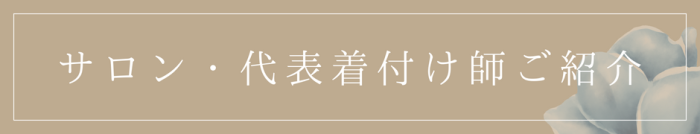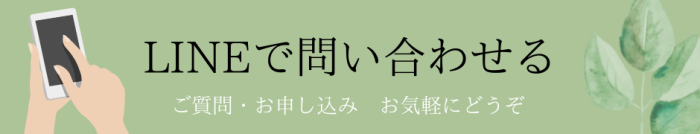七五三は、子どもの成長を祝う日本の伝統行事で、元々は平安時代から続く宮中や武家社会の「通過儀礼」がルーツです。単なるイベントごとと捉えられがちですが、七五三を迎えるにあたり今一度3歳5歳7歳の七五三、それぞれの由来を年齢別に解説します。
3歳/髪置(かみおき)の儀
対象年齢:3歳女児
起源:平安時代の宮中儀礼
背景:昔は赤ちゃんのときに髪を剃る習慣があり、3歳頃から髪を伸ばし始めることを祝いました。
目的:髪置の儀では、3歳を迎える頃に髪を伸ばすことで「健康に育ちますように」と願いを込めていました。
補足:この頃の儀式では、白髪に見立てた白糸や綿帽子を頭に乗せる所作もありました。これは長寿の象徴である「白髪」にあやかるためです。

5歳 /袴着(はかまぎ)の儀
対象年齢:5歳男子
起源:平安時代の男子の初儀礼、または武家における初めての正装
背景:男児が初めて袴を着ける儀式。これは古くは元服(げんぷく)という成人儀式の前段階にあたる儀礼です。
目的:武家社会の儀式が始まりで、男の子が「社会の一員として成長していく節目」を祝いました。強く、立派な男子に育つよう願いを込めた行事です
補足:使用する袴は縞袴(しまばかま)や仙台平(せんだいひら)など、格式のある織物が使われることが多く、儀式の際には羽織袴姿で行うのが正式とされています。

7歳 /帯解(おびとき)の儀
対象:7歳女の子
起源:室町時代以降、武家や上流階級の子女に行われた儀式
背景:それまで子ども用の着物に用いられていた付け紐(つけひも)を外し、大人と同じく本格的な帯を結ぶことを許される通過儀礼です。
目的:女の子が一人前の女性に近づく第一歩とされ、成長を祝う大切な通過儀礼でした。
:この帯解の儀は、成人への準備としての意味合いが強く、精神的な成長だけでなく、礼儀や身だしなみにも意識を向けるようになる転換期とされていました。

現代では、儀式的な意味合いは薄れつつありますが、七五三は依然として「子どもの健やかな成長を感謝し、祈る日」として大切にされている、愛情たっぷりの日本の伝統行事なんですね😊
他にも七五三に関する知識やお役立ち情報を発信しています→関連記事はこちら