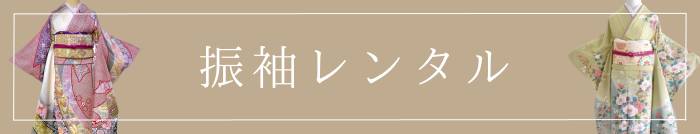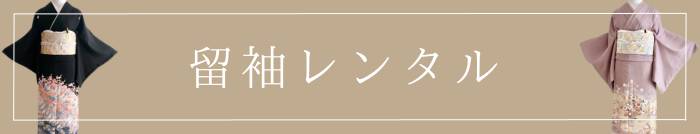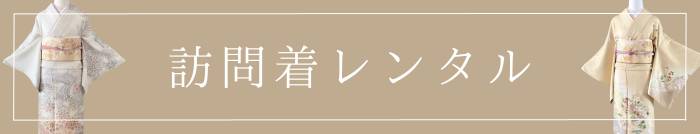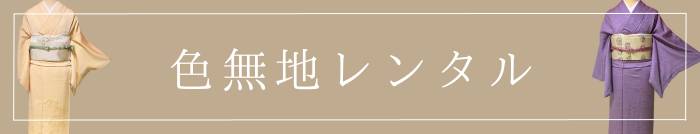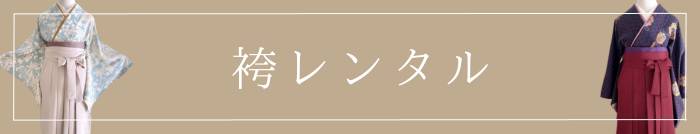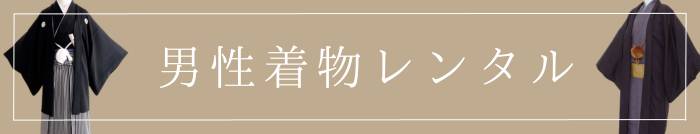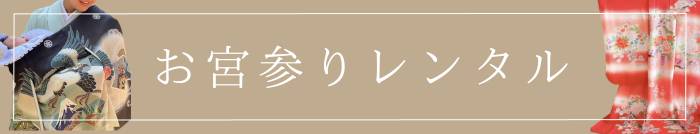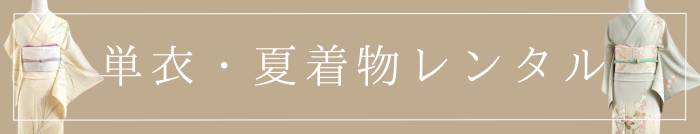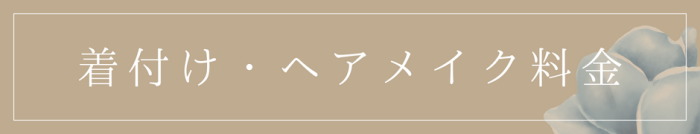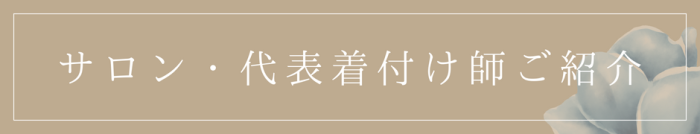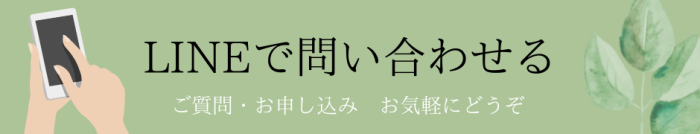実は七五三で使われる髪飾りや小物には、どれも日本の美しい伝統や「子どもの健やかな成長を願う想い」が込められています。以下に代表的なものとその意味を丁寧にご紹介しますね。
🌸 七五三の髪飾りと込められた意味
① ちんころ(ちんころ)
意味:魔除け・厄除け
特徴:ちりめんや絹で作られた細長い紐状の髪飾りで、髷(まげ)の根元などに巻いて使います。
② かのこ(鹿の子絞り)
意味:長寿・魔除け・子孫繁栄
特徴:絞り染めで鹿の背の模様のような斑点模様を表現。主に髪に巻いたり帯に使われます。
由来:鹿は「長寿」の象徴とされ、鹿の子模様には縁起が良い意味が込められています。
③ つまみ細工
意味:華やかさ、成長、花のように美しく育つ願い
特徴:小さな布を折りたたんで作る花型の細工。簪(かんざし)や髪飾りとして用います。
由来:江戸時代から伝わる伝統工芸。季節の花をかたどることが多く、女の子の優雅さ・可愛らしさを引き立てます。
④ 簪(かんざし)
意味:大人の女性の象徴、厄除け、守護
特徴:金属や木製、漆塗りなど様々な素材でできた髪飾り。花簪・玉簪・房付き簪など種類も豊富。
由来:日本髪を整えるための実用的な道具であり、身を清める意味もある伝統的な装飾。


🎀 七五三の小物と込められた意味
① 帯揚げ・帯締め
意味:気品・大人らしさ・格式
特徴:帯の上に飾る布や、帯を結んで整える紐。色・柄で晴れの日らしさを演出します。
由来:本来は機能的な装飾ですが、「帯をしっかり結ぶ=心身を引き締める」という意味合いも。
② しごき(志古貴)
意味:成長、身分の証、美徳の象徴
特徴:帯の下に結ぶ長い布で、腰から後ろに垂らすように結びます。
由来:もとは武家女性の裾さばきを良くするための実用品。後に礼装として取り入れられ、女児の華やかさを演出します。
③ お守り袋(おまもりぶくろ)
意味:無病息災、厄除け
特徴:神社でいただく守り袋のほか、着物とコーディネートした刺繍入りのおしゃれなお守り袋もあります。
由来:神仏に子どもの健康と成長を祈願した証として身に着けます。
④ 扇子(せんす)
意味:お守り・縁起物
特徴:扇子が「末広がり」に開くことから、将来の繁栄や幸せを願う縁起物でもあります
由来:昔から、扇子は礼儀や儀式の場で使われる大事な道具。武家の女性やお姫様の装いに欠かせないものでした
⑤箱迫(はこせこ)
意味:七五三では「大人の女性の仲間入り」という意味を込めて使われます
特徴:小さな箱の形をした飾りで、帯の間に差し込みます。中には昔はお金やお香などを入れていたことも
由来:江戸時代、上流階級の女性が使っていた持ち物。大人っぽい装いの象徴として、今も七五三などで使われています
⑥ 草履(ぞうり)
意味:大人の装いへの一歩
特徴:女の子は草履に合わせた巾着型バッグを持つことが多いです。男の子は雪駄(せった)や下駄も選ばれます。
由来:外出=社会に出ることの象徴。「一歩ずつ成長していく」意味合いを持ちます。

たまに7歳の七五三でしごきが見当たらないけど、本当に必要ですか?とお尋ねになる方もいらっしゃいますが、スタイルはもちろん、意味合いの上でも全ての小物は必要なものなんです。
伝統の中に、親の深い愛情や祈りがこめられていますね…✨
他にも七五三に関する知識やお役立ち情報を発信しています→関連記事はこちら